冬休みが近づくと塾から冬期講習の案内が届きます。
「受けなかったら出遅れてしまうのでは?」
「でも費用も高いし、うちの子に合うのかな…」
中学受験を控えるご家庭なら、一度はそんな迷いを抱いたことがあるのではないでしょうか。
実際、冬期講習は受験直前期の総仕上げとして大きな役割を果たしますが、必ずしも“全員に必要”とは限りません。むしろ受けないことで、自宅学習に集中し合格を勝ち取った子もいます。
この記事では、
「冬期講習を受ける/受けない」それぞれのメリット・デメリットや、家庭でできる学習法、実際の体験談 を紹介します。
親としての不安を整理しながら、子どもにとって最適な冬休みの過ごし方を一緒に考えていきましょう。
最後までお付き合いいただければ、幸いです!
冬期講習は本当に必要?中学受験生の実態

中学受験における冬期講習の位置づけ
冬期講習は受験直前の総仕上げとして位置づけられています。
塾からの案内には「この講座が合否を分ける」と強調されることもあり、親としては「受けないと取り残されるのでは」と不安になるものです。
ただ実際には、全員にとって必須ではありません。
子どもの学力や志望校、そして家庭の方針によって必要性は変わってきます。
冬期講習を受けない選択肢とは
「塾に行かない=不安」という気持ちは当然です。
ですが、冬期講習を受けないことで、自宅で過去問演習や苦手克服にじっくり取り組めるメリットもあります。周りに流されず、子どもに合った学び方を選ぶ勇気も必要です。
講習のメリットとデメリットを考える
- メリット:
・塾のカリキュラムに沿って安心して勉強できる
・周りの子と刺激し合える
・志望校別の対策が受けられる - デメリット:
・費用が高い
・スケジュールがぎっしりで子どもが疲れやすい
・個別の弱点に十分時間を割けない。
「子どもの負担」と「親の安心感」のバランスをどう取るかが大きなポイントです。
合格への道:受講の必要性を再考
塾は「講習に参加すること」を前提に案内しますが、本当に大事なのは「子どもにとって一番効果的な勉強ができているか」。
冬期講習はあくまで“手段”であり、受けるか受けないかは家庭ごとに最適解が違います。
模試と過去問:冬期に何を重視すべきか
冬休みに一番大事なのは「過去問演習」と「模試の振り返り」です。
冬期講習に参加するかどうかに関わらず、この2つをしっかりやることが合格への近道です。
冬期講習を受けない理由とその影響
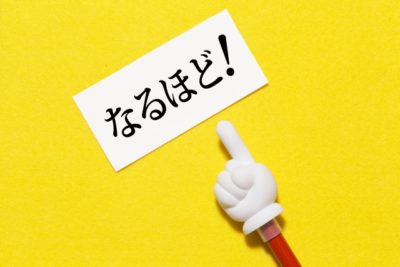
自宅学習の利点とその方法
「塾に行かなくても、本当に大丈夫?」と思う親御さんは多いですが、自宅学習には大きな利点があります。
子どもの理解度に合わせた勉強ができ、ペースを崩さず進められるのです。
たとえば、模試の直しを一緒に見直したり、弱点ノートを作ったりするだけでも、十分力はつきます。
時間の有効活用:冬休みの勉強計画
冬休みは短く、予定も多い時期です。講習に行くと移動や拘束で1日がほぼ終わってしまうことも…。自宅なら「午前は過去問」「午後は暗記」「夜は間違え直し」とメリハリをつけた勉強ができます。親子で一緒に1日の学習計画を立てると、安心感も生まれます。
家庭でできる復習法と教材選び
「塾に行かない分、教材はどうする?」という心配もあります。市販の総復習ドリルや通信教育、場合によってはオンライン家庭教師をポイントで利用すれば十分補えます。親が一緒に選んであげることで、子どもも前向きに取り組めます。
お金をかけずに合格を目指すための工夫
冬期講習費用は数万円〜十数万円。決して軽くない出費です。その分を家庭学習用教材や家庭教師数回分に充てた方が、結果的に効果的なケースもあります。「塾に通わない」選択は決してマイナスではありません。
冬期講習参加の準備と心構え

志望校別の講座選びのポイント
受講するなら「とりあえず全部」ではなく、志望校別や弱点補強に的を絞りましょう。親が冷静に取捨選択することで、子どもの負担も減ります。
苦手教科を克服するための特訓法
「算数の応用問題だけ」「国語の記述だけ」など、苦手科目だけピンポイントで受けるのも有効です。無理に全教科を詰め込むよりも、弱点克服に集中した方が成果につながります。
先生とのコミュニケーションで得られる情報
講習中は先生に声をかけるチャンス。模試の成績を見てもらい「あとどこを強化すべきか」を確認すれば、冬休み後の勉強に自信が持てます。
正月を利用した学習の計画とは
正月はどうしても気が緩みます。「せめて朝1時間は机に向かう」など、小さな習慣を決めるとリズムを崩さずに済みます。親が一緒に時間を区切るだけで、子どもも安心して取り組めます。
実際の受験生の体験談

冬期講習を受けた生徒の声
「周りの子が頑張っている姿に刺激を受けた」
「志望校対策で同じ問題形式を解けて自信になった」など、良い刺激を得られたという声も多いです。
冬期講習を受けなかった生徒の成功事例
一方で「冬休みは過去問に集中して第一志望に合格した」
「家庭教師を週1回入れて弱点だけ直した」など、講習に行かなくても成功した例は珍しくありません。
要は「講習の有無」ではなく「どう学習を積み上げたか」が合否を分けるのです。
具体的な冬休み学習スケジュール例
冬休みは短期間だからこそ、毎日の学習リズムを整えることが合否を左右します。ここでは 冬期講習を受ける場合 と 受けない場合 のモデルケースを紹介します。
あくまでも一例です。ご参考までに。
冬期講習を受ける場合の1日(例)
- 7:00〜8:00 朝の計算・漢字・暗記(講習前に基礎固め)
- 9:00〜15:00 塾の冬期講習(昼休憩含む)
- 16:00〜17:00 帰宅後の休憩・軽食
- 17:00〜18:30 講習で解いた問題の復習
- 19:00〜20:30 過去問の一部を解く/弱点補強
- 21:00〜21:30 親子で振り返り&翌日の準備
👉 ポイントは「講習内容をその日のうちに復習」すること。やりっぱなしにせず、1日の学習を定着させましょう。
冬期講習を受けない場合の1日(例)
- 7:00〜8:00 計算・漢字・理科社会の暗記
- 9:00〜11:00 過去問演習(本番と同じ時間を測って解く)
- 11:00〜12:00 過去問の直し・解説確認
- 13:00〜15:00 苦手科目の徹底復習(算数応用/国語記述など)
- 15:30〜16:30 休憩後、基礎問題集で弱点補強
- 17:00〜18:00 暗記タイム(理科用語・社会年号など)
- 19:00〜20:00 短時間の過去問解き直し、模試の復習
- 20:00〜21:00 親子で1日の振り返り・学習計画の修正
冬休み中のNG行動(やってはいけない過ごし方3選)

① 過去問を解きっぱなしにする
「解くだけで勉強した気になる」ことは最大の落とし穴です。
間違えた問題を放置すると、せっかくの冬休みが“できない問題の再確認”で終わってしまいます。必ず直しをして「なぜ間違えたのか」を確認しましょう。
② 夜型に崩れて生活リズムを乱す
冬休みは夜更かしになりがちですが、本番の入試は朝から始まります。夜型に崩れると当日のパフォーマンスに直結します。
朝型の生活リズムを維持することが合格力につながると心得ましょう。
③ 「とりあえず全部やる」と詰め込みすぎる
冬休みは短いため、あれもこれもと手を出すと中途半端で終わってしまいます。
大切なのは「取捨選択」。優先順位を決めて「ここを伸ばせば合格に近づく」というポイントに集中しましょう。
✨ まとめると、冬休みに大切なのは
- 「過去問→復習」の徹底
- 朝型リズムの維持
- 優先順位を決めて学習に集中
この3つです。
冬期講習に参加するかしないかよりも、 冬休みをどう過ごすか が合否を分けます。親子で安心して受験直前期を乗り切れるよう、無駄のない計画を立てていきましょう。
まとめ:冬期講習の選択が合格に与える影響
自分に合った学習法を見つける大切さ
冬期講習を受けるかどうかは、子どもの学習スタイル・家庭の方針・志望校対策の進み具合で決めるべきです。大事なのは「周りが行くから」ではなく、「本当に自分に必要か」を見極めること。
受験対策における意識改革の必要性
中学受験は「塾のカリキュラムをこなすこと」が目的ではありません。志望校合格というゴールに向けて、最適な方法を選ぶ柔軟さが求められます。冬期講習に参加するかしないかは通過点にすぎず、最後に勝つのは「自分に合った勉強をやり切った子ども」です。
第一志望校に合格されるよう、心より応援しております!
